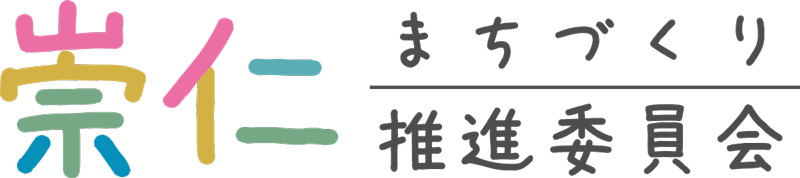2025年4月18日崇仁の祭囃子 なんでも Q&A
―参加者募集!―
京都市下京区崇仁学区に伝わるお囃子、お祭りに参加してみませんか。
京都芸大の移転で崇仁学区の町並みはさらに変わりつつありますが、
お囃子の音色は、今も昔も変わりません。
地域の人々の心と身体に刻まれてきたメロディー・リズムを受け継いで、
盛り立てていくことを目的とするQ&Aです。
◆参加資格は?
・やってみたい人なら、どなたでも参加できます。京都市下京区崇仁学区の皆さんが中心のお囃子・お祭りですが、周辺地域の皆さん、京都芸大の学生・留学生・教職員も多数参加しています。
・お囃子・お祭りともに経験は問いません。笛は篠笛(しのぶえ)を使いますが、フルート、リコーダー等の経験者、初めてのかた大歓迎です。
・稽古料・参加費等は不要です。
・練習時の服装は自由です。持ち物もとくに不要ですが、篠笛、リコーダーをお持ちのかたは持参してください。
◆お囃子の練習は、いつ、どこで?
・第1木曜日 19:00~20:00
・第4土曜日 16:00~17:00
・場所:下京青少年活動センター(須原通り塩小路下る)1階奧の会議室
(ロビー受付前を通り、マットと下駄箱のある所で靴を脱いでお入りください)
・随時、見学・体験を受け付けていますので、お気軽にお越しください。
・毎年4月から5月上旬にかけて、お祭りの本番に向けた集中稽古も行います。会場を京都芸大にうつした出張稽古も行っています。
・お囃子は、5月のお祭り(第2日曜、崇仁春祭りの鉾巡行)で演奏します。イベント出演、奉納演奏などもあります。
・練習など活動の主催者は、「崇仁お囃子会」です。文化庁などの助成も受けています。
・問い合わせ先 メール info@sujin.jp(崇仁まちづくり推進委員会)
京都芸大での出張稽古(A棟1階 伝音セミナールーム、2024年6月)
◆お祭りは、いつ、どこで?
・5月に「崇仁春祭り」が開催されます。鉾(ほこ)を大勢で曳いたり、お囃子を演奏します。警察署の協力で安全に、車道を練り歩きます。どなたでも参加できます。
・日時:5月 第2日曜日 午前の部、午後の部
・集合場所と巡行コースは、4月にポスター・web等でご案内します
・崇仁春祭りの主催・運営は、崇仁自治連合会、崇仁祭り実行委員会です。
・雨天中止ですが、お囃子の披露のみ行う場合もあります。
・問い合わせ先 メール info@sujin.jp(崇仁まちづくり推進委員会)
2019年5月の崇仁春祭り。大学移転前から京芸の学生・教職員、区役所・消防署の有志が多数参加しています。鉾・山車は、2006年に京都市登録有形民俗文化財に指定されています。
◆お囃子・お祭りの魅力は?
・歴史に触れる、町に親しむ
江戸末期から伝承される貴重なお囃子・お祭りを体験できます。一時中断した時期もありましたが地元の皆さんの熱意で復活し、昔と変わらないお囃子・お祭りを伝えています。
お祭りの巡行のとき皆で引っ張る大きな鉾は、京都祇園祭の鉾に比べると小型でかわいらしいものですが、かつての祭の発展とともに装飾と意匠が凝らされた雅やかなもので、京都市有形民俗文化財に指定されています。
・共感を深める
子どもから大人まで、世代を越えて集まり、一緒に取り組むことで、多くの人々と交流しながら共感を深めます。お祭りの巡行では、ふだんと異なる町の表情を大勢で共有して楽しみます。
崇仁学区と芸大・他地域の「結線」としての役割も大きく、かけがえのない存在です。

2023年10月1日 京都芸大移転記念 開校式典での祝賀演奏(出演:崇仁お囃子会、京芸生ほか有志)
・芸能の伝承を担う
お囃子・お祭りに参加することは、京都の文化財である芸能の伝承、伝統を担う一員になることを意味します。先輩から後輩へと受け継がれていくお囃子・お祭りの芸と真髄。その責任を感じながら、楽器の奏でる芸能に触れる楽しみ、その体験を深めていくことは有意義で貴重です。
多くの皆さんの協力、参加によって、たとえ町並みが変わろうとも、お囃子・お祭りは変わることなく続けられていくのです。
・楽器の奏でる音の世界へ
お囃子は単調な繰り返しに聞こえるかもしれませんが、鉦・太鼓は一定のテンポを保つのが難しく、笛は音を出すのも息を保つのも難しい楽器です。しかし、稽古を繰り返していくと、鉦・太鼓・笛の奏でる音の世界に没入していきます。
ときに力強く、ときに繊細で味わい深い、お囃子の不思議な魅力の虜になるでしょう。
◆お囃子・お祭りへの地域の皆さんの思いは?
・昭和の中断から平成の復活へ
・功労者藤本さん
・鉾の修理
・有形文化財指定
(以上、原稿準備中です)
◆お囃子の楽器は?
主な楽器は、鉦(かね)、太鼓(たいこ)、篠笛(しのぶえ)の3種類です。
▶鉦(かね)
あたり鉦ともいいます。京都祇園祭の祇園囃子、京都の六斎念仏でも使われています。鉦には長い紐が付属し、鉦吊りに結びつけて使用します。
鉦を叩くバチは、「鉦すり」などと呼ばれます。バチの先端部分は鹿角、持ち手は鯨の髭(歯の一部)で作られますが、現在はさまざまな素材が用いられています。
▶太鼓(たいこ)
小型の太鼓で、木製の持ち手がついています。大・小、2つのサイズがあります。太鼓を叩くバチは、樫などの木製です。
お祭りの巡行では、持ち手を握って歩きながら立奏するのが基本ですが、稽古や演奏会では座奏もします。
また、六斎念仏と同様に、太鼓を振り回す所作や、4つの太鼓を台に据えて曲芸的な打ち方をする「曲打ち」も伝承されています。
▶篠笛(しのぶえ)
竹を加工して作られた笛です。調律・ピッチは、京都の六斎念仏の篠笛と同じです(千本六斎会の吹田会長の御教示による)。
漆など塗料を塗ったもの・塗らないもの、プラスチック製のものなど、さまざまな素材の篠笛が使われています。お囃子会が楽器店に特注して誂えたものや市販の既成品のほか、吹き手が自作した笛も大活躍しています。
京都芸大竹内研究室では、お囃子会と共同して、電動工具を使って笛を自作するワークショップも随時実施しています。
なお、篠笛のパートをリコーダーで吹いて参加することも可能です。笛の吹き手は慢性的な不足に悩まされていますので、手持ちのリコーダーで気軽にご参加ください。
◆お囃子の楽譜は?
お囃子の稽古は昔から、耳・声・目など、からだ全体を駆使して、先輩から後輩へと芸を伝えていく「口頭伝承」を基本とします。鉦・太鼓の叩き方、笛の吹き方を図式化・譜面化した見取り図のような、先輩方の自作の楽譜も昔から存在し、先輩方がその都度の工夫を重ねて楽譜を作成し後輩と共有することもあります。しかし、何よりも実際の音をよく聞いて、確実にまねる(まねぶ=学ぶ)ことが最も大切で、上達の早道です。
楽譜を使わずに耳で聞いて覚えたり演奏することは、お囃子のような民俗芸能だけでなく、Jポップ、ジャズやロック、カラオケ等でも同様ですよね。
◆お囃子の曲目は?
現在の伝承曲は、3つです。
1「だんじり」
通称「オハヤシ」と呼ばれて、もっとも親しまれています。お祭りの鉾巡行のときに、歩きながら演奏します。巡行で曳き歩く「鉾」「山車」のことを、かつては「だんじり」とも呼んでいたので、だんじり用のお囃子という意味からの名称であると考えられます。
京都の六斎念仏に広く伝承される演目「祇園囃子」と酷似していること、昭和の中断前と平成の復活後の伝承の真正性に疑いがないとの伝承者の証言が得られていることから、この地域で江戸時代から行われていた柳原六斎念仏の伝承をそのまま現在に受け継いでいると考えられます。六斎念仏ではこの曲をお祭りの巡行時に使うことはないので、六斎念仏の伝承曲としては希少な演奏形態を有することになります。
六斎念仏本来の伝承よりも、太鼓の力強い躍動的なリズムが特徴です。これは崇仁のお祭り巡行に特有のイキの良さ、地域の皆さんが祭にかける情熱が、次第にお囃子へ付加されていった結果としての躍動感であろうと想像しています。
2「ぎおんばやし」
平成のお囃子復活の際に追加された新しい伝承曲です。平成の復活時に助言を受けた岩戸山(京都祇園祭)のお囃子から移させていただいたものなので、元来は京都祇園祭の伝統的なお囃子です。笛の旋律に、しっとりした深い趣があります。
3「よつだいこ」
太鼓と笛、または太鼓のみで演奏。4つの太鼓を台に固定し、曲芸的な手順の打ち方を交えながら、小気味よく、目まぐるしいバチさばきで叩いていく、太鼓メインの曲です。
京都の六斎念仏に広く行われている人気演目で、やはり江戸時代の柳原六斎念仏からそのまま崇仁お囃子会へ継承されてきたと考えられます。
◆柳原六斎念仏とは?
「柳原」は、崇仁学区の地域旧称です。柳原六斎念仏は、江戸後期~幕末に発祥し、昭和中期まで伝存していました。昭和初期の六斎念仏の太鼓が、現在も崇仁のお囃子で修理を重ねて大切に使用されています。柳原六斎念仏という名前は今では馴染みが薄くなってしまいましたが、崇仁のお祭り巡行にそのお囃子が「だんじり」「よつだいこ」が現在まで生き永らえているのです。
六斎念仏は、主に関西圏に広く分布する念仏講の一種で、公家や大店の葬礼の鳴物をつとめるなどして発展し、京都の周辺農村部を中心に20以上の講(伝承団体)がありました。幕末までには、獅子舞などの祝福芸、能楽、歌舞伎、三味線音楽などの影響も受けるようになって芸能化が進み、新たな芸態と演目を次々に増やしていきました。
清水寺の古文書によると、柳原六斎念仏は江戸後期から盛んに行われ、清水寺で行われた六斎競演会の常連だったそうです。現在の他の六斎念仏講と同様に、かつては柳原でも10以上の演目が華々しく行われていたのでしょう。その証拠として、柳原六斎念仏の獅子舞などの道具も保存されています。
そうした痕跡を手がかりに、地域の皆さんと芸大生が協力して、柳原六斎念仏としての新たな復活を果たしてくれることを願っています。
出典:『崇仁のまつり』柳原銀行記念資料館 第16回特別展 図録(2005年)
◆お祭りの鉾(ほこ)はどんなもの? お祭りの歴史は?
現存する鉾(ほこ)と山車(だし)
1 船鉾(西浜組)(塩小路高倉に展示)
2 十二灯(巽組、山車(ダンジリ))(塩小路須原通に展示)
3 船鉾(碇組)(塩小路須原通に展示)
4 子ども船鉾(ミニチュア)
新日吉神社について
御旅所について
(以上、原稿準備中です)

5月第2日曜日にお囃子とともに崇仁学区を巡ります。

◆崇仁の祭囃子を知るための主な資料
■文献
1 京都市文化観光局文化財保護課編 1985年 『崇仁地区祭礼調査概要』京都市
2 柳原銀行祈念資料館編 2005年 『崇仁のまつり』柳原銀行記念資料館 第16回特別展 図録
3 竹口等 2001年 「崇仁地区の新しいまちづくり―その前夜 祭囃子に引き寄せられて」京都文教大学人間学研究所紀要『人間学研究』2号
4 竹口等 2003年 「音を復元する―崇仁祭囃子とまちづくり」『京都フィールドワークのススメ』昭和堂
5 福持昌之 2022年 「崇仁の祭り囃子」『京都の祭り・行事―地蔵盆とコロナ禍の地域行事』京都ふるさと伝統行事普及啓発実行委員会
■動画
日本伝統音楽研究センター 2022年 公開講座「崇仁の祭り囃子—もう一つの六斎念仏—」 ※28分から模範演奏(字幕解説付き)(日本伝統音楽研究センターYouTubeチャンネル)
■自習用の模範演奏(2000年7月収録「だんじり」、崇仁お囃子会提供)
模範演奏(ここをクリックしてダウンロード、MP3形式、4MB)
■楽譜例(作成:竹内研究室)
だんじり 見取図(五線譜).pdf
この楽譜は、あくまで全体の構成と流れを、視覚的に把握するためのメモで、演奏の規範・模範ではありません。旋律とリズムの委細は、実際の稽古や録音の模範演奏をよく聞いて耳で音を覚え、再現することが重要です。
———————————————————————————
(本コラムの作成者)
京都市立芸術大学 音楽学部(音楽学特講)
大学院音楽研究科(音楽学特殊研究)
2024年度履修学生有志
日本伝統音楽研究センター 竹内有一研究室
2024年7月編集開始
2025年4月公開開始